 KEI
KEIこんにちは!KEIです。



皆さんはバイクの整備を自分で行うことはありますか?
本日は自分でバイクを整備するときに必ず必要になる「工具」。
こちらのおすすめセットをご紹介します!
バイクを手に入れたばかりの初心者ライダーの中には、「そろそろ自分でも簡単なメンテナンスをしてみたい!」と考える方も多いでしょう。
その第一歩として欠かせないのが「工具セット」。
とはいえ、工具って種類も多く、どれが必要なのか、どこで買うべきか分からない…と迷ってしまうのも当然です。
この記事では、初心者に必要な工具の基本と、失敗しない工具セットの選び方、そしておすすめ商品5選まで詳しく紹介していきます。
さらに、工具を使う際の注意点や、よくあるミス、長く使うための保管方法も含めて解説します。
なぜ工具セットが必要なの?
バイクは日常的なメンテナンスをしてあげることで、寿命も快適さも大きく変わってきます。
初心者でも挑戦しやすい整備としては、
- チェーンの張り調整・注油
- バッテリー端子の点検
- ミラーやレバーの交換
- オイル交換 など
これらを行うには、最低限の工具が必要になります。
ショップに任せると費用も時間もかかりますが、自分でできればコストを抑えられる上、愛着も湧いてくるのがバイクの面白いところです。
自分で整備することで、バイクの構造や弱点が理解でき、万が一のトラブル時にも冷静に対処しやすくなります。
ちょっとした異音や挙動の変化にも気づきやすくなり、結果としてバイクの寿命や安全性を高めることにもつながります。
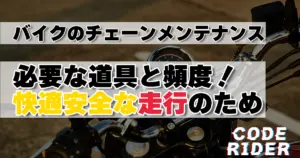
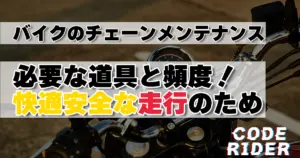
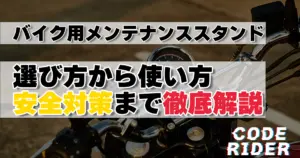
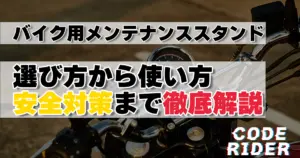
工具セットを選ぶ時のポイント
① 必要な工具が揃っているか
バイクを整備するためには以下のような工具が必要です。
もちろんバイクによっても変わってきますので、下記は一般的な必要工具になります。
- ラチェットレンチ&ソケット(8mm〜14mm)
- コンビネーションレンチ(スパナ&メガネ)
- プラス・マイナスドライバー
- 六角レンチ(ヘキサゴン)
- モンキーレンチ
- ペンチ類(プライヤーなど)
- トルクレンチ(できれば)
これらはほとんどのバイクで共通して使われるサイズと種類なので、最初に揃えておくと多くの作業に対応できます。



バイクによっては工具が変わってくるので、自分のバイクを確認しましょう!



特にハーレーに乗っている方はメートル工具ではなく、インチ工具をそろえる必要があるので注意です。
② 工具の材質と作りの質
安価すぎる工具は折れたり曲がったりして危険です。
特にネジ山をなめやすい初心者こそ、ある程度信頼できるメーカー製を選びましょう。
「クロームバナジウム鋼」などの素材表記があるものは、耐久性や錆びにくさで安心です。
また、グリップが握りやすい形状かどうかも要チェックです。
③ ケース付きかどうか
バラで揃えると管理が面倒なので、専用ケースに収まっているセット品は持ち運び・保管に便利です。
特にツーリング先や屋外で作業をすることが多い場合、コンパクトにまとまっているかどうかは重要なポイントになります。



ボックスに入っているタイプだとまとめて持ち運びができるので、整備性が上がります!
④ 安心できるメーカーの高い工具は良い
「高い工具でも安い工具でも使用用途は同じでしょ?安い工具でいいじゃん。」
そう思われる方もいると思います。
ですが、これは大きな間違いです。
高い工具にはやはり高い工具の性能があります。
わかりやすいところですと高い工具は寸法や作りがしっかりしているものが多く、ねじやナットをなめることが少ないです。
また、工具自体の耐久年数もあり、力を加えやすいといった工夫も施されているものが多いので
実は整備初心者の方ほど高い工具をおすすめしたいです。
初心者におすすめのバイク用工具セット5選
トネ(TONE)
言わずと知れた日本を代表する工具メーカー。
プロも愛用している。
- 特徴:圧倒的な品質の良さと耐久性の良さ
- 価格:10,000円~
- メリット:工具の品質が良く、ねじやボルトをなめにくい
- デメリット:他メーカーと比較すると高価



費用面が問題なければ非常にお勧めできる工具メーカーです!
一生モノの工具にもなれるポテンシャルを十分に秘めています。
SK11
信頼の工具ブランドSK11による本格セット。
- 特徴:実用性重視、車両整備にも使える頑丈な工具多数
- 価格:4,000円~
- メリット:工具の耐久性が高く、長く使える
- デメリット:価格がやや高め
アストロプロダクツ
整備好きにはおなじみの工具専門店。
- 特徴:ショップ品質に近い構成、コスパ良し
- 価格:10,000円~
- メリット:価格と性能のバランスが良い
- デメリット:地方には店舗が少ないため通販がメイン



筆者はアストロプロダクツを愛用しています!
価格と性能のコスパが最高で使いやすいです!
KTC
プロ仕様で有名なKTCの入門向けセット。
- 特徴:精度・耐久性抜群。価格は高めだが一生モノ
- 価格:約60,000円〜
- メリット:信頼と安心の国産ブランド
- デメリット:価格がネックになりやすい
イーバリュー(E-Value)
安価な工具が多くそろっており、コスパが良い。実は日本製。
- 特徴:選び抜かれたツールが揃っており、コンパクトで機能的
- 価格:約10,000円前後
- メリット:10,000円ほどで工具一式をそろえることが可能
- デメリット:価格相応の工具であり、あまりプロは使用しない



まずは簡単な整備からやってみたいという方にはおすすめできる工具です!
整備についてやっていく中で工具をレベルアップさせていく使い方がよいと思います!
工具使用時の注意点とよくある失敗例
ネジ山をなめる
初心者にありがちなミスです。
ネジ山をドライバーなどで欠けてしまうと、それ以上ネジをまわせなくなってしまいます。
このような状態無理に回す前にネジのサイズや向きを確認しましょう。



固いネジを緩めるときはショックドライバーや貫通ドライバーがあると便利です!
トルクのかけすぎ・不足
締め付けすぎてパーツが破損したり、緩すぎて走行中に外れるケースも。
トルクレンチの使用を検討することをおすすめします。



「回らなくなるまで締め付ければいいんでしょ?」と思いがちですが、ねじを折ったりする可能性があります。



力任せに作業してしまうと取り返しのつかないことになることも…
工具の使い方を間違える
モンキーレンチを適当に使ってネジを潰すなど、適切な工具を正しい位置で使うことが重要です。



これどうやって使うんだろう?といった工具がある場合は事前に調べてから使用しましょう。
工具と一緒に揃えたいおすすめアイテム
- トルクレンチ:締め付けすぎ・緩み防止に
- グリス・潤滑スプレー:チェーンメンテに必須
- メンテナンススタンド:リアホイールの持ち上げで作業効率UP
- 使い捨て手袋・ウエス:作業後の手やパーツの汚れ防止に
- LEDライト:暗いガレージや夜間整備時に活躍
- パーツトレイ(マグネット付き):ネジやボルトを紛失しないために



トルクレンチは何でもいいわけではなく、自分のバイクに使用するトルク値に対応しているものを購入しましょう!
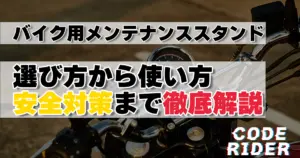
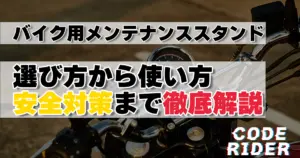
工具を長持ちさせるための保管・メンテナンス方法
- 使用後は必ず汚れを拭き取る
- 湿気を避け、乾燥した場所に保管する
- 定期的にサビ止めスプレーを使用
- ケースがある場合は必ず収納し、紛失を防ぐ
長く使うことで、工具にも愛着が湧き、整備のモチベーションもアップします。
まとめ:まずは基本を揃えて少しずつステップアップ
バイクのメンテナンスは「工具が揃っていれば怖くない」。
最初から完璧な整備を目指す必要はありません。
まずは簡単な作業から始めて、必要に応じて工具や知識を増やしていけばOKです。
オイル交換やミラー交換など簡単な作業から行って、整備の知識を身に着けていきましょう!
そして、自分で整備ができるようになると、より深くバイクを楽しめるようになります。
今回紹介した工具セットは、どれも初心者にとって扱いやすく、コスパに優れたものばかり。
ぜひ、自分のスタイルに合った1セットを手に入れて、快適で安心なバイクライフをスタートさせましょう!



Xもフォローいただけますと大変喜びます!


バイクを売るときできるだけ高価格で売りたいと思いますよね。
でもいちいち買い取り店を回るのも面倒だし、一括見積は営業の電話やメールが多くて避けたい…。
そんな時に「KATIX」!
KATIXなら営業の電話やメールも来ませんし、複数業者が入札を行っていくので高価格な買取が期待できます!
自宅で手軽に自分のバイクの価値を調べてみませんか?
詳しくは下記解説記事をご覧ください!
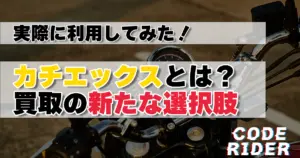
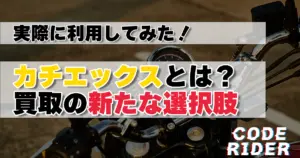


新作のバイクウェアやヘルメットはついつい欲しくなりますよね。
そんな時に困るのが古いバイクウェアやヘルメットの処分。
メルカリ等は手間が面倒だし、リサイクルショップじゃ二束三文にしかならない…。
そんな方にお勧めなのが「グッドエンド」!
バイク用品のネット買取専門店だからこその安心感があります。
詳しくは下記解説記事をご覧ください!
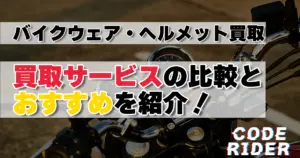
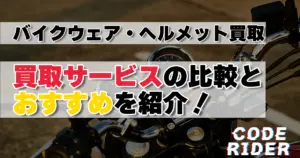
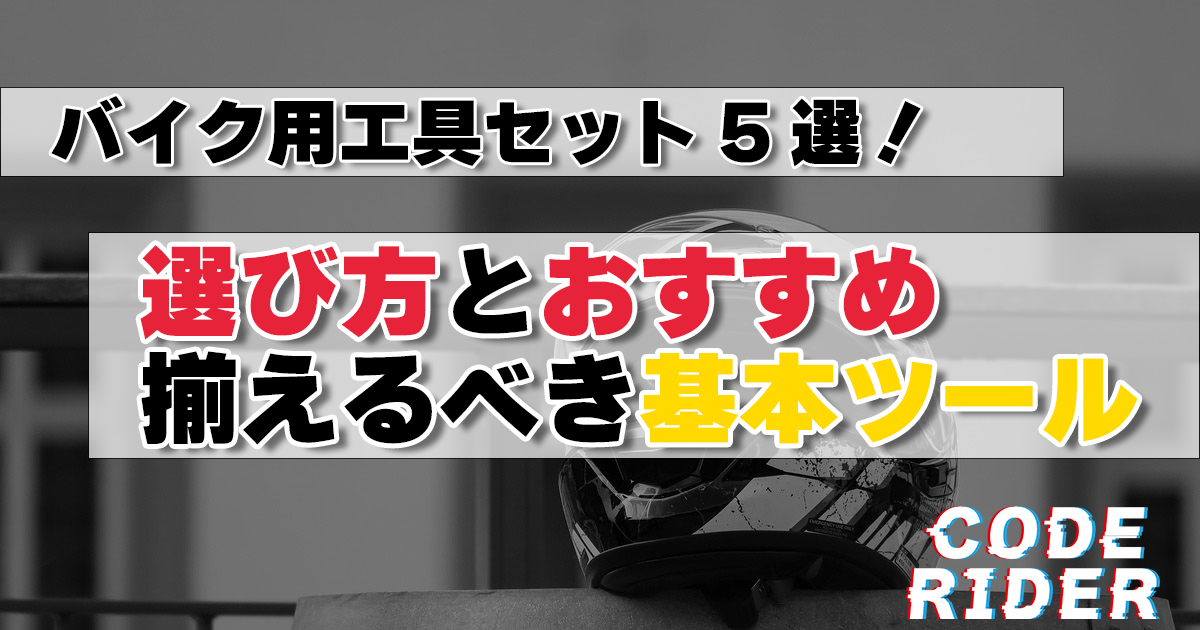
コメント